2016年 撮影紀行(その6)
8月15日〜16日 高川山
満月の明かりに照らされる雲と、夏の風物詩といえる富士山道の明かりを撮るため高川山を訪れることにした。夏になると富士山の山道には明かりが灯され、特に満月の夜は幻想的な異次元の世界を覗き見ることが出来る。その山道の明かりは天に向かいあたかも天と地の架け橋のような情景が思い浮かぶ。この時期ならではの風物詩と云っても良い。
満月日は18日(木)で2日程早いが月の明るさには変化はない。問題は天気である。予報では午前4時から晴のマークが付いているが、前倒しで0時頃から晴れて月が出てくれれば意図した写真が撮れる可能性がある。月没は2時で三ツ峠の山頂に沈むが、それまでが撮影チャンスである。
15日午後21時20分、初狩側登山口を出発。薄いガスが立ちこめ無風で蒸し暑い。今回も男坂コースを登り、女坂コースを下山する予定である。
女坂、男坂の分岐点に21時50分に到着。分岐点の直前は傾斜のある登り坂が続き、運動量の多さに汗の噴出量が半端でない。その湿気と熱でメガネは曇り視界が確保できず外して歩くことにする。男坂は名の通り後半ロープの張られた急斜面の岩場を登るが暑さで体力が消耗しペースがやや落ちる。合流点を22時35分に通過。ここで一息付く事が出来る。山頂までは比較的緩い斜面が続き山頂は間もなくである。
山頂到着は23時00分。ガスが立ちこめ、月も星も見えず視界が閉ざされている。暫く様子を窺うが一向に状況に変化はない。0時を過ぎた頃から予想に反し雨が降り出す。小雨程度であったが時間を追うに従い雨足が強まる一方。間もなく止むだろうと高を括っていたが雨足は更に強さを増してきた。防雨対策はしてきたものの、強い雨は予測していなかっただけにレインウエアーでも追いつかず、身体はずぶ濡れ状態。機材を濡らさないようにするだけで精一杯。
雨が止んだのは3時になってからである。月没時間は既に過ぎている。これで意図した写真は撮れず終いとなったが、取りあえず撮影準備を始める。その後、30分程して視界が開いた。雲海の中に富士山が浮かぶが、ガスにまみれで鮮明な姿は見られない。天空は曇り空、星空も見られない。雲海は小規模でそのトップは低く街灯りが透けて見える。
日の出時間5時01分(東京)であるが、東の空は色付いているものの光はなく薄暗い。その後、5分もしないうちに視界は閉じた。この山頂がガスに被われた状況から恐らく雲海に飲みこまれていたものと思われる。再び視界が開いたのは4時間後、9時になってからである。富士山は雲に覆われ山頂の一部が姿を現したが、間もなく雲の中に姿を消した。雲海はトップの位置も高く大雲海に発達していた。
山頂には強い日差しが降り注ぎ、濡れた衣服を乾かすことが出来たが、富士山は一向に姿を現さない。暫くこの状態は続くと思われた。照りつける日差しの中、これを期に10時00分、山頂を後に下山を始める。
女坂コースの登山道は水分を多く含み滑り易い状態となっていたため下山時間を多く要した。登山口に戻ったのは11時40分。これまで誰とも出会うことはなかったが、登山口で山頂に向かう男性2人の登山者と出会った。
今回は山頂に約11時間滞在したが、視界が開いたのは3時30分から5時00分までの約1時間30分だけであった。台風の影響もあり天候に恵まれず、残念ながら満足な写真は撮らせて貰えなかったが、多少なりとも善し悪しは別として、富士山の写真が撮れただけでも運が良かった。
今日の富士山
雲海の下に街灯りが透けて見える 3:55 頃 |
雲海のボリュームが増してきた
4:20頃 |
雲海トップの位置が徐々に高く
なってきた 4:30頃 |
 |
 |
 |
山頂および登山道の状況
山頂の様子
| ヘクソカズラ(アカネ科) 悪臭がする |
ママコナ(ゴマノハグサ科) |
不明(調査中) |
マルバハギ(マメ科) |
 |
 |
 |
 |
ヤマグリの実(ブナ科) |
高川山山頂 9:55頃 |
山頂直下に群生するママコナ 9:55頃 |
岩の多い山頂からの下山道 10:00頃 |
 |
 |
 |
 |
登山道の状況
| オクモミジハグマ(キク科) 10:00頃 |
山頂直下の分岐点 10:05頃 |
岩が散乱している下山道 10:15頃 |
男坂・女坂の分岐点 10:15頃 |
 |
 |
 |
 |
| 比較的緩やかな女坂コース 10:20頃 |
女坂途中の崩落地 | アキノタムラソウ(シソ科) 10:45頃 |
不明(調査中) 10:50頃 |
 |
 |
 |
 |
| 男坂・女坂合流点 10:20頃 |
合流点直下の斜面はきつい 11:05頃 |
黄色い立ち入り防止ネット 11:10頃 |
 |
 |
 |
登山口付近の状況
登山口近くの登山道11:20頃 |
登山口に咲くヤマアジサイ (ユキノシタ科) |
女坂・男坂登山口 11:30頃 |
 |
 |
 |
ヤマホトトギス(ユリ科) |
シロヨメナ(キク科) |
ヨメナ(キク科 ) |
 |
 |
 |
使用カメラ(デジタル) ・OLYMPUS E-M1 ・FINEPIX F1000EXR
8月3日 清八山
前日の2日は関東甲信地方全般に降雨予報があり、山沿いでは降水量も多いとの情報があった。これで大地に水分が蓄えられ大月の山でも雲海の発生があると予想された。当日の天気は全日曇りの予報で、雲海が発生しても富士山の姿が無ければ撮影にならず、徒労に終わる可能性が有る。当日の予想天気図を見る限り高気圧は前日よりも広がりが見られ、雲の合間から富士山が姿を現す可能性は十分あると推測された。
今回は本年初めてとなる十二景の山では最も富士山に近い清八山から雲海と富士山を狙うことにした。清八山へは夏冬関わらず毎回大月側から短時間で登れるコースを使っている。このコースは笹子追分から南に向かう林道終点の登山口まで車で行き、そこから山頂に登るコースである。
林道終点の登山口に到着したのは午前1時50分。未だ雨は止まず登るかどうか躊躇したが、山の天気は登ってみなければ分からないというのが正直な気持ちである。2時15分、登山口を出発。暫く小高い丘を登るが、この一帯には檜の苗が植林されている。2009年に檜は全面的に伐採され、その翌年に苗木が植えられた。現在未だ人の背丈に満たない檜が育ちつつあるが、主伐まで50年以上という長い年月を要するようである。途中で間伐もあり、林業の1サイクルは長く、大変な仕事だと改めて認識させられた。最近このコースを利用する人は少ないのだろうか。草木が背丈以上に伸び登山道が何処にあるのか見当が付かない。掻き分けて登山道を確認しながら登るが小雨が降る中、草木の水滴もあり、身体は早くもずぶ濡れ状態である。
30分程掛かって小高い丘を登り終えると山道に入る。登山道はしっかり付いていて不明瞭な所は無いが、斜面がきついためつづら折りに切られたハードな上り坂が暫く続く。中腹のベンチのある休憩所には3時20分に到着。休憩せずそのまま山頂に向かう。小雨は降り続き止むような気配は無い。風は無風でかなり蒸し暑く、汗と湿気で眼鏡はくもり、更にガスが発生していて視界が殆ど利かないため眼鏡を外して歩く。
清八峠には4時10分到着。ここまで来ると山頂は間もなくである。 4時20分山頂到着。小雨は降っているが、なんと富士山が姿を見せている。ガスっぽく抜けは良くないが、周辺の谷は雲海で埋め尽くされている。予想通りの展開に感動は隠せないが、いつ視界が閉じるか分からない状況にあり急いで撮影準備に入る。
10分程すると雨は止み視界が抜けてきた。しかし、未だ夜が明け切らず光りも弱く薄暗い。東の空は赤味を帯びているが、全般に曇り空で、日の出時間に朝日が届くか分からない。 時折、雲の合間からスポット的に青空が見え隠れする。日の出時間(東京4時50分)に富士山に絡む雲が一瞬焼け出した。シャッターチャンスとばかりにそのシーンはカメラに収めたが、束の間の出来事だった。その後、朝日が届くことはなく、5時20分富士山は雲の中に姿を消した。
暫く待機するも富士山はなかなか姿を現さない。やっと7時になって視界が開け富士山が姿を現した。しかし、雲海トップが水平だった雲はばらけた雲に変化している。更にガスが立ち込め、抜けが良くない。30分程すると再び視界は閉じた。山頂はガスで被われ、雲海に飲みこまれたようである。
こうなると視界は暫く開かないと思われながらも待機したが、天気の回復は見込めず8時50分山頂を後にした。 途中、青空が広がり太陽の陽を浴びたが、身体が冷え切っていたせいか暑さはそれ程感じない。小高い丘の上で景色を眺めながら休憩を15分程取り、登山口には10時50分に戻った。
今日も登山者やカメラマンなど誰とも出会うことはなかった。
今日の富士山
日ノ出時間帯の富士山 4:55頃 |
2回目視界が開いた時の富士山 7:20頃 |
 |
 |
山頂および登山道の状況
御坂黒岳の勇姿 5:35頃 |
山頂に咲く ホツツジ
(ツツジ科) |
清八山山頂 8:55頃 |
山頂から清八峠に向かう
登山道 8:55頃 |
 |
 |
 |
 |
清八峠 9:00頃 |
清八峠からの下山道 9:05頃 |
中腹の休憩所 9:40頃 |
群生しているヒヨドリバナ
10:20頃 |
 |
 |
 |
 |
小高い丘の上からの展望 10:05頃 |
 |
ヤマホタルブクロ
10::20頃 |
登 山者カード提出箱
10:50頃 |
登山道入口(案内板あり)
10:50頃 |
登山口付近に止めた車
10:50頃 |
 |
 |
 |
 |
行程:登山口(2:15発)→小高い丘頂部(山道入口)(2:45)→ベンチのある休憩所(3:20)
→清八峠(4:10)→山頂(4:20着〜8:55発)→清八峠(9:00)
→ベンチのある休憩所(9:35)→小高い丘頂部(10:05〜10:20)→登山口(10:50)
使用カメラ(デジタル) ・OLYMPUS E-M1 ・FINEPIX F1000EXR
7月4日 高川山
高川山を訪れるのは今年1月以来半年ぶりである。今回は夜景を撮影する目的で計画をした。高川山は街灯りや富士山山道の明かりが灯され夜景を撮影するには絶好の場所である。夜景は基本的にバルブ撮影(長時間露光)をするため1枚撮影するのに時間が掛かる。このため、時間に余裕を持たせる必要があり午前0時には山頂に到着して撮影を始める予定を考えた。
今回も初狩側の登山口から男坂コースで山頂に登り、下山は女坂コースから沢コース(玉子石コース)に分岐し登山口に戻るという行程である。
3日、22時30分に登山口を出発する。天空を仰ぐと満天の星空、気温、湿度共に高いことから天空の抜けは良いとは云えないが山頂からは改善されていると思われる。夜景を撮るには絶好の条件と思われるが、この暑さでは天気の急変も考えられる。歩く前から汗が滲んでいたが、暫く歩くと汗の噴出は半端ではない。
男坂、女坂の分岐点を22時55分に通過。途中からロープの張った急斜面に入るが思うように登ることが出来ない。吐き気とめまいが同時に襲う。熱中症の症状と思われた。今回は夜中の撮影となるため登山口には早めに到着し、2~3時間でも仮眠できればと思い車中仮眠をしたが、暑くて殆ど寝ることは出来なかった。この時も汗だくで相当量水分が失われていた。このようなことが影響し熱中症の症状が現れたと思われる。道半ばであるが暫く休憩し、水分補給と共に回復を待った。30分程で症状は緩和され登山を再開した。
男坂、女坂の合流点を23時50分に通過。山頂には午前0時15分に到着。天空は抜けて星が輝きを見せている。風は無風、汗で濡れた衣服が乾くことなく更に汗を重ねている状況である。一息付いた後、撮影準備に入る。
バルブ撮影は1枚撮るのに30分程時間を要し、日の長い時期は午前2時半頃になると空は白みだし、星は肉眼では確認出来なくなる。この時間は星空と富士山を撮影するタイムリミットである。東の空は日の出の準備でオレンジ色に染まっている。殆ど雲のない状態だったが、日ノ出が近づくにつれ上空の雲が増え、天気は少しずつ悪化に向かっているようである。
日ノ出時間4時30分(東京)を迎えた。富士山上空の色が俄に色付きだした。富士山頂にはあまり形の良くない雲が纏わり付き、朝焼けはしたものの撮影意欲が湧いてこない。
時間の経過と共に靄が濃くなる傾向があり、5時40分富士山撮影を打ち切る。その後、雲は更に増え、天気は徐々に悪くなる傾向を示している。
暫く山頂の花などを撮影し、6時45分下山を始める。女坂コースから沢コースを下り、登山口には7時55分到着。暫くすると1台の車が止められた。男性3人組の登山者で高川山へ登ると云って出発していった。
今日の富士山
午前2時頃まで空は抜け星が綺麗に輝いていたが、その後靄が発生し鮮明さが失われてきた。
山頂への登山道に明かりが灯されている
0:50頃 |
山頂には当初から笠雲が掛かっている
1:05頃 |
 |
 |
密集した星の光跡 2:00頃 |
笠雲を突き抜けた山頂の明かり 3:15頃 |
 |
 |
山頂および登山道
山頂の様子
山頂に咲く オカトラノオ
(サクラソウ科) |
山頂に咲く シモツケ
(バラ科) |
虹が発生 6:30頃 |
山頂の山名標柱 6:40頃 |
 |
 |
 |
 |
登山道の様子
下山時に撮影したものを時間順に並べてある
山頂直下の下山道
7:00頃 |
男坂、女坂の合流点
7:00頃 |
女坂途中の崩落跡
7:05頃 |
沢コースへの分岐点 7:15頃 |
 |
 |
 |
 |
沢コースの登山道 7:20頃 |
途中から舗装された
林道になる 7:30頃 |
コースの名称となっている
玉子石 7:40頃 |
いわれは不明だが“柱石”
7:45頃 |
 |
 |
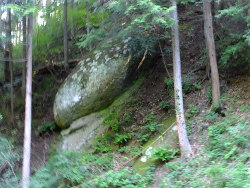 |
 |
檜林の中に敷設された林道
7:45頃 |
男坂女坂コース入口
7:50頃 |
林道脇に群生する
オカトラノオ 7:50頃 |
トイレのある登山口広場
7:55頃 |
 |
 |
 |
 |


